生地黄(しょうじおう)
※ 桃華堂では生薬単体の販売はしておりません。お取り扱いのない商品についてのお問い合わせはご遠慮ください。
基原
ゴマノハグサ科ScrophulariaceaeのジオウRehmannia glutinosa Libosch.またはその変種のカイケイジオウRehmannia glutinosa Libosch.var hueichingensis Chao et SchihあるいはアカヤジオウRehmannia glutinosa Libosch.var purpurea Mak.の肥大根
性味
甘・苦、寒
帰経
心・肝・腎
効能・効果
①清熱滋陰
②涼血止血
③生津止渇
主な漢方薬
竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)
消風散(しょうふうさん)
五淋散(ごりんさん)
炙甘草湯(しゃかんぞうとう)
清営湯(せいえいとう)
犀角地黄湯(さいかくじおうとう)
大補陰丸(だいほいんがん)
益胃湯(えきいとう)
特徴
ジオウは中国の砂質地や荒れ地に生育する多年草です。日本にはかなり昔に渡来し、「延喜式(927年)」に山城で栽培していたという記録が残っています。奈良県橿原市の地黄町は、鎌倉時代にジオウの産地だった名残です。赤紫色を帯びた長さ3~4cmほどの筒型の綺麗な花をつけますが観賞用として植えられることは少なく、生薬原料として畑か薬用植物園などで栽培されています。
地黄は加工方法の違いによって効能が大きく異なります。鮮地黄(せんじおう)は新鮮なもので清熱涼血・止血に働き、生地黄(しょうじおう)・乾地黄(かんじおう)は乾燥品で涼血滋陰・清熱に働き、熟地黄(じゅくじおう)は何度も酒で蒸し晒す過程を経て熟製したもので滋陰補血の効能を持ちます。加工方法によって効能が変わる理由は、蒸しと乾燥を繰り返すことにより徐々に配糖体と呼ばれる成分の糖が切断され、成分や糖の含量が変化するためです。日本では地黄と言えば乾地黄のことを指しますが、中国では熟地黄のほうが補血、滋陰の力が強いとされ、四物湯(しもつとう)や六味地黄丸(ろくみじおうがん)などには熟地黄が用いられます。鮮地黄は外面が淡黄赤色、熟地黄は漆黒色、乾地黄はその中間の色をしています。日本薬局方では乾地黄と熟地黄を区別せず、単に地黄としています。鮮地黄は日本ではほとんど使用されていません。熟地炭は炭化させたもので止血に用います。
広西省ではキク科植物の根を生地あるいは土生地として利用するので注意が必要です。
「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)」の上品に「乾地黄」の名で収載され、生のものが最も良いとの記載がみられます。
火熱が血に及んで出血や発熱するものを治療する清熱涼血薬(せいねつりょうけつやく)に分類され、同じような効能を持つ生薬に犀角(さいかく)・牡丹皮(ぼたんぴ)・赤芍(せきしゃく)があります。
生地黄と犀角はともに涼血清熱の効能を持ち、血分実熱に用いられます。違いとしては、犀角は解毒に優れ、生地黄は滋陰に優れているため、血熱毒盛には犀角が、陰血不足には生地黄が適しています。
温熱病の熱入営血による夜間の発熱・熱感・口乾などの症状に用いられます。代表的な漢方薬に、犀角や金銀花(きんぎんか)などと一緒に配合された清営湯(せいえいとう)があります。
熱盛傷津による便秘に、玄参(げんじん)や麦門冬(ばくもんどう)などと一緒に用いられます。
熱病後期で微熱が続くときあるいは慢性病の陰虚発熱に用いられます。代表的な漢方薬に、知母(ちも)と一緒に配合された大補陰丸(だいほいんがん)があります。
陰虚の喉痛には、甘草(かんぞう)や薄荷(はっか)などと一緒に用いられます。
血熱妄行による吐血・鼻出血・血尿・血便・性器出血などに用いられます。
熱入営血による紫黒色の皮下出血や他の出血に用いられます。代表的な漢方薬に、犀角や赤芍などと一緒に配合された犀角地黄湯(さいかくじおうとう)があります。
熱盛傷津による口乾・口渇・口唇の乾燥などに用いられます。代表的な漢方薬に、麦門冬や玉竹(ぎょくちく)などと一緒に配合された益胃湯(えきいとう)があります。
消渇証の口渇・多飲に、山薬(さんやく)や枸杞子(くこし)と一緒に用いられます。
脾虚有湿で腹満・泥状便を呈するときには用いてはいけません。
LINEで完結♪
オーダーメイド漢方治療
LINEで完結♪
オーダーメイド漢方治療
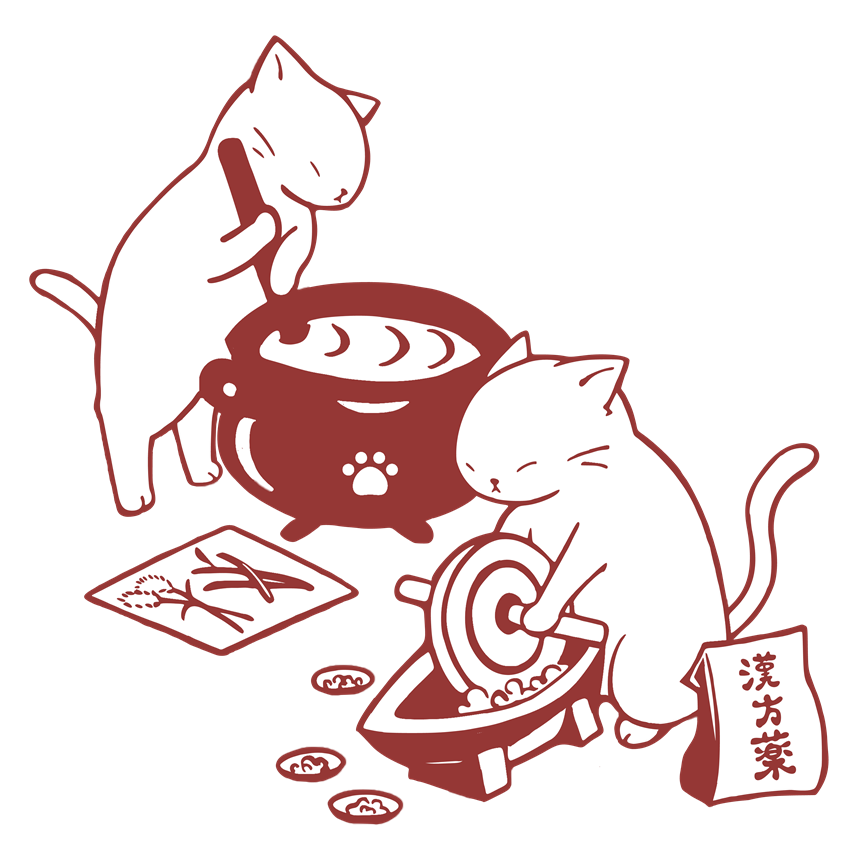
漢方専門の薬剤師があなたに
ぴったりの漢方薬をご提案
まずはLINEより無料の
体質診断をしてみましょう!
― 初回限定 ―
\桃華堂オリジナル缶プレゼント!/
LINE相談について詳しくはこちら ↓

