山薬(さんやく)
※ 桃華堂では生薬単体の販売はしておりません。お取り扱いのない商品についてのお問い合わせはご遠慮ください。
基原
ヤマノイモ科DioscoreaceaeのナガイモDioscorea batatas Decaisneの外皮を除去した根茎(担根体)。日本産はヤマノイモDioscorea japonica Thunbergに由来する
性味
甘、平
帰経
脾・肺・腎
効能・効果
①補脾止瀉
②養陰扶脾
③養肺益陰・止咳
④補腎固精・縮尿・止帯
主な漢方薬
六味地黄丸(ろくみじおうがん)
知柏地黄丸(ちばくじおうがん)
八味地黄丸(はちみじおうがん)
参苓白朮散(じんりょうびゃくじゅつさん)
牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)
啓脾湯(けいひとう)
特徴
ヤマノイモはつる性の多年草で、本州以南に分布しています。ヤマイモ科ヤマノイモ属の植物は世界に600種以上あり、日本では長芋や自然薯、銀杏芋、大和いもなどが食されています。ヤマノイモの語源は、里でとれる里芋に対して山の芋と言われたことからきています。地下にある芋は普通で数十センチ、長いもので1.5メートルに達し、自然薯や山芋とも言われています。使用部位は茎と根の中間型で、植物形態学上正しくは担根体(たんこんたい)と称します。
芋を掘るのは冬ですが、その頃には地上部が枯れてしまい、どこを掘ったら良いのか分からなくなります。そこで、まだ茎のあるうちに目印の棒をさしたり、麦を一掴み根本にまいて、棒や麦の茂っている所を見つけて掘ります。細い特殊な鍬を使って掘りますが、長くて折れやすいうえに、他の植物の根などがあって掘り上げるのにはかなりの根気が必要です。掘るのに労力がかかることと、すり鉢とすりこ木がくっついてしまうほどの濃厚なとろろ汁になるため、自然薯は高級食材となっています。秋に葉の脇にできるムカゴもおいしく、ご飯に炊き込んだり、油で炒っておつまみにもなります。
栄養が豊富で、消化酵素のジアスターゼを多く含むので消化吸収もよく、古くから「山のうなぎ」と言われるほど精力がつくことで知られています。
ヤマノイモは日本原産で国内の山林に広く分布し、初夏に白い小さな花を咲かせます。一方、中国ではヤマノイモとよく似ているナガイモが山薬として使用されます。ナガイモは日本には自生しておらず、昔から東北を中心に日本各地の畑で栽培されていました。「日本薬局方(にほんやっきょくほう) 」 では 両者とも山薬の基原植物となりますが、市場品として流通しているのはナガイモの方です。ナガイモはヤマノイモと比べて茎が紫に色づいており、葉が丸みを帯びて上部が張り出しています。他にもよく似た植物にオニドコロやニガカシュウなどの同属植物が見られますが、苦いため食用には適しません。
薬用部位は周皮を除いた担根体で、秋に掘り出した根茎を洗浄して周皮を除き、乾燥させたものを用います。さらに太いものを水に浸けて加熱し 、柔らかくして円柱状に成形し、乾燥させた後に磨いて白くまっすぐに加工したものが「 光山薬 」と呼ばれています。また、中国薬典では「毛山薬」と呼ばれる山薬もあり、こちらは根頭を除いて洗浄し 、外皮とヒゲ根を除いて乾燥したものを指します。
白色または類白色で、質が重く滑沢のあるものが良品とされています。
山薬は「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)」の上品に「薯蕷(しょよ)」の名で収載されています。山薬という名前に変わった理由は、唐代の皇帝の代宗の名が蕷であったので、それを避けて「薯薬」となり、その後宋代の皇帝の英宗の名が署であったので山薬と改められました。
「本草綱目(ほんぞうこうもく)」で李時珍は「薬に入れるには野生のものが勝り、食品としては栽培したものを良しとする」と述べられています。
気虚(エネルギー不足)を改善する補気薬(ほきやく)に分類され、同じような効能を持つ生薬に人参(にんじん)、党参(とうじん)、西洋参(せいようじん)、白朮(びゃくじゅつ)、黄耆(おうぎ)、甘草(かんぞう)、大棗(たいそう)、膠飴(こうい)などがあります。
脾虚による食欲不振・元気がない・泥状~水様便・食べると排便するなどの症状に用いられます。代表的な漢方薬に、人参(にんじん)や白朮と一緒に配合された参苓白朮散(じんりょうびゃくじゅつさん)や啓脾湯(けいひとう)があります。
脾陰虚による食欲不振・食べると腹が張る・口乾などの症状に、単味あるいは蓮子(れんし)や薏苡仁(よくいにん)などと一緒に用いられます。
肺虚(気陰不足)の慢性咳嗽・呼吸困難などの症状に、麦門冬(ばくもんどう)や五味子(ごみし)などと一緒に用いられます。
腎虚の遺精・縮尿・白色帯下などの症状に用いられます。代表的な漢方薬に、熟地黄(じゅくじおう)や山茱萸(さんしゅゆ)と一緒に配合された六味地黄丸(ろくみじおうがん)や八味地黄丸(はちみじおうがん)があります。
養陰には生用し、健脾止瀉には炒用します。
山薬と白朮は補脾止瀉に働き、脾虚泄瀉によく一緒に用いられます。山薬は甘平で健気と養陰に働き肺腎も補益し、渋性があるので肺虚喘咳・消渇・遺精・帯下などにも有効です。白朮は苦温で補中益気・燥湿健脾に働き、脾虚の吐瀉以外に痰飲水腫・表虚自汗に有効です。山薬は湿盛中満には禁忌であり、白朮は陰虚津少には禁忌です。
養陰助湿するので、湿盛・中満・積滞には用いません。
LINEで完結♪
オーダーメイド漢方治療
LINEで完結♪
オーダーメイド漢方治療
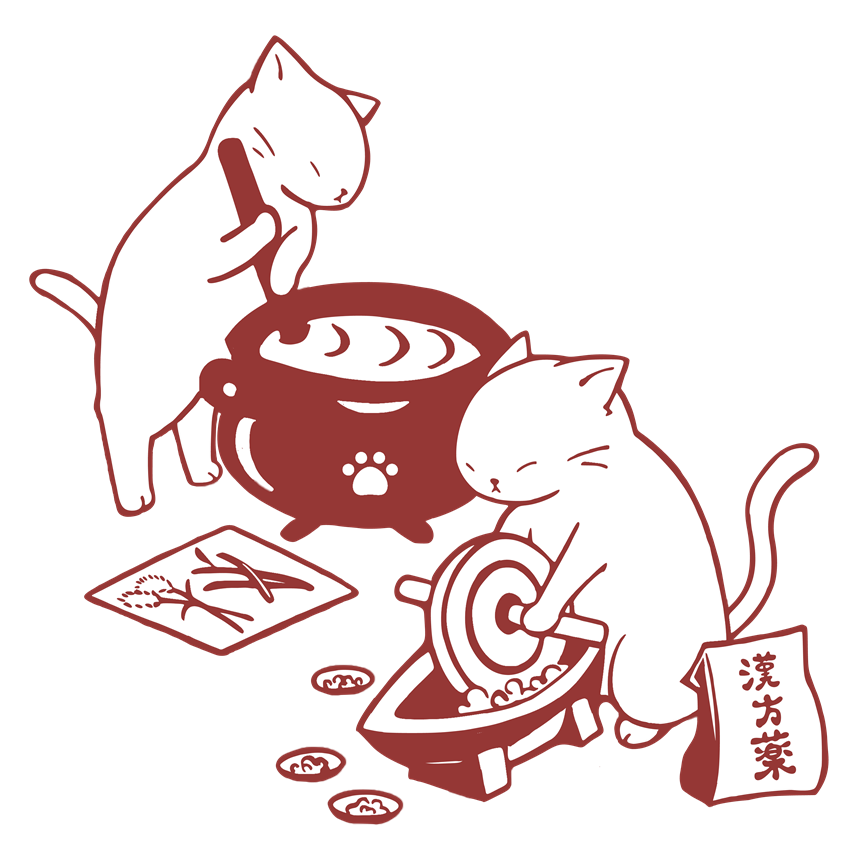
漢方専門の薬剤師があなたに
ぴったりの漢方薬をご提案
まずはLINEより無料の
体質診断をしてみましょう!
― 初回限定 ―
\桃華堂オリジナル缶プレゼント!/
LINE相談について詳しくはこちら ↓

