玄参(げんじん)
※ 桃華堂では生薬単体の販売はしておりません。お取り扱いのない商品についてのお問い合わせはご遠慮ください。
基原
ゴマノハグサ科Scrophulariaceaeのゴマノハグサ属植物Scrophularia ningpoensis Hemsl.の根
性味
苦・鹹、寒
帰経
肺・胃・腎
効能・効果
①滋陰涼血・除煩
②滋陰降火・解毒
③清熱軟堅
④潤腸通便
主な漢方薬
加味温胆湯(かみうんたんとう)
清熱補気湯(せいねつほきとう)
清営湯(せいえいとう)
養陰清肺湯(よういんせいはいとう)
増液湯(ぞうえきとう)
神仙太乙膏(しんせんたいつこう)
特徴
ゴマノハグサはゴマノハグサ科の多年草で、湿気のある草地に生息しています。ゴマノハグサの名前の由来は「胡麻の葉草」から来ており、葉が胡麻の葉に似ていることからつけられたと言われています。現在ゴマノハグサは日本で絶滅危惧II類に指定されています。
中医学の五行に、色の違う5つの人参を当てはめた「五参」というものがあります。李時珍(りじちん)は「五参はその五色がそれぞれの五臓に配するものだ。人参は脾に入るから黄参といい、沙参(しゃじん)は肺に入るから白参といい、玄参は腎に入るから黒参といい、牡蒙は肝に入るから紫参といい、丹参(たんじん)は心に入るから赤参という」と記しています。また、「玄とは黒色のことである」とも記されており、玄参の名前が黒色の人参からきていることがわかります。
外皮は淡褐色、内部は黒色で、粘り気があり肥大したものが良品とされています。
体を潤す滋陰薬(じいんやく)に分類され、同じような効能を持つ生薬に沙参(しゃじん)、浜防風(はまぼうふう)、天門冬(てんもんどう)、麦門冬(ばくもんどう)、黄精(おうせい)、百合(びゃくごう)、玉竹(ぎょくちく)、旱蓮草(かんれんそう)、枸杞子(くこし)、女貞子(じょていし)、亀板(きばん)、鼈甲(べっこう)があります。
「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)」の中品に収載されており、古くから「足の少陰、腎経の君薬」とされ、滋陰降火の常用薬です。
湿熱の邪による夜間光熱・意識障害などに用いられます。代表的な漢方薬に生地黄(しょうじおう)や丹参と一緒に配合された清営湯(せいえいとう)があります。
陰虚火旺(いんきょかおう:体の潤い不足によって相対的に陽が亢進する状態)による喉の痛みや目の充血・のぼせ・咳嗽などに用いられます。代表的な漢方薬に生地黄や牡丹皮(ぼたんぴ)と一緒に配合された養陰清肺湯(よういんせいはいとう)があります。
潤い不足による便秘に用いられます。代表的な漢方薬に地黄や麦門冬(ばくもんどう)と一緒に配合された増液湯(ぞうえきとう)があります。
同じゴマノハグサ科の生薬に地黄があります。両者の効能はよく似ていますが、生地黄は甘潤で滋養の力が玄参よりも強く、玄参は苦鹹降泄し降火の力が強いです。生地黄は陰血不足に適し、玄参は陰虚火旺に適するほか、解毒にも働きます。
生薬の配合で混ぜると毒性が強く出やすい組み合わせを「十八反(じゅうはっぱん)」と言います。玄参もこの中に含まれており、配合禁忌とされている生薬は藜芦(りろ)です。藜芦は玄参以外にも人参(にんじん)、丹参(たんじん)、西洋参(せいようじん)、苦参(くじん)、沙参(しゃじん)、細辛(さいしん)、赤芍(せきしゃく)、白芍(びゃくしゃく)とも相反します。
脾胃に湿のある方や、脾が衰弱して軟便の方には禁忌です。
LINEで完結♪
オーダーメイド漢方治療
LINEで完結♪
オーダーメイド漢方治療
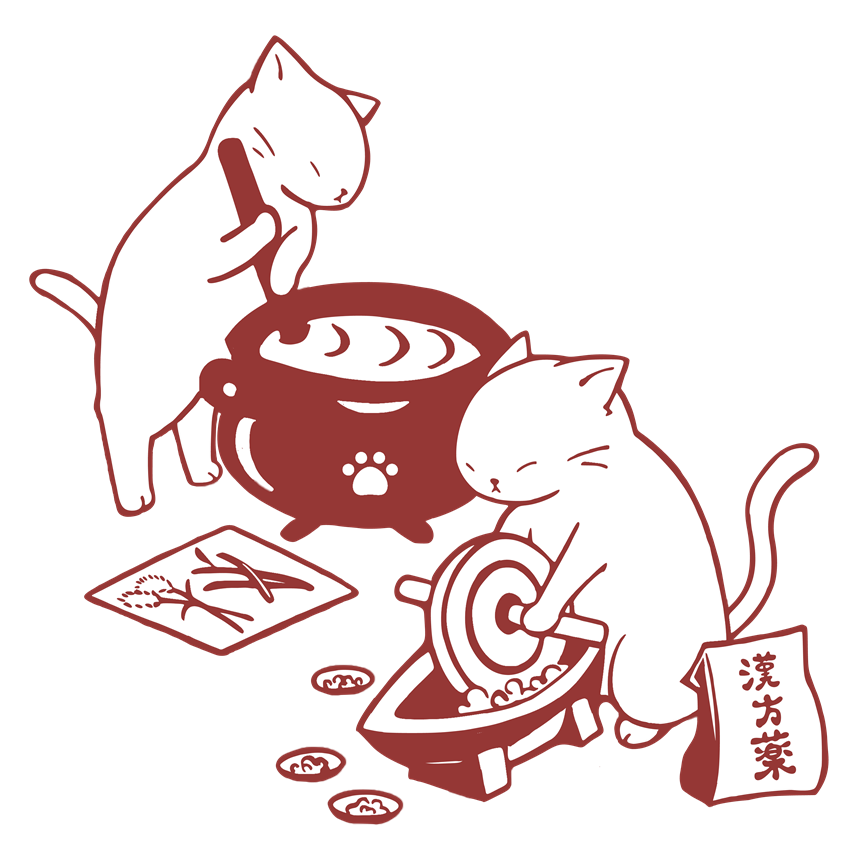
漢方専門の薬剤師があなたに
ぴったりの漢方薬をご提案
まずはLINEより無料の
体質診断をしてみましょう!
― 初回限定 ―
\桃華堂オリジナル缶プレゼント!/
LINE相談について詳しくはこちら ↓

