黄連(おうれん)

※ 桃華堂では生薬単体の販売はしておりません。お取り扱いのない商品についてのお問い合わせはご遠慮ください。
基原
キンポウゲ科 Ranunculaceaeのオウレン Coptis japonica Mak.およびその他同属植物の根をほとんど除いた根茎
性味
苦、寒
帰経
心・脾・胃・肝・胆・大腸
効能・効果
①清熱燥湿
②清熱瀉火
③清熱解毒
主な漢方薬
温清飲(うんせいいん)
黄連阿膠湯(おうれんあきょうとう)
黄連解毒湯(おうれんげどくとう)
葛根黄連黄芩湯(かっこんおうれんおうごんとう)
荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)
三黄瀉心湯(さんおうしゃしんとう)
清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)
半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)
特徴
黄連は日本固有種で、北海道南西部、本州、四国、九州に分布する常緑の多年生草木です。古くから日本に自生している植物で、民間薬として整腸剤や胃薬に配合されていました。直射日光や乾燥に弱く、山地の樹陰など、落ち葉が降り積もっている湿った場所に自生します。花は白色の五弁の花で、とても可愛く園芸用としても親しまれています。根茎が黄色で、節が珠を連ねたようであることから、「黄連」と名付けられました。
中国から黄連の知識が日本に伝わったのは奈良時代です。多くの生薬は中国産のものを使いますが、黄連は日本に野生種としてあったものを代替品として用いていました。日本産の黄連は品質がよいとされ、江戸時代には野生品の黄連を中国に輸出し、日本各地で黄連の栽培化も盛んに行われました。元々日本で使われていた黄連のほとんどは日本産のものでしたが、最近は中国産のものが多く出回っています。現在は日本産と中国産の両者の品質に差はほとんどないと言われています。
黄連の苦味の正体はベルベリンという成分で、黄連が黄色なのもベルベリンの影響です。ベルベリンの薬効は胃腸機能の促進・抗菌作用・下痢止め・血圧降下・抗炎症作用など多岐にわたります。ベルベリンは黄連以外に黄柏(おうばく)にも含まれています。
熱を冷まして湿邪(しつじゃ)を除く清熱燥湿薬(せいねつそうしつやく)に分類され、同じような効能を持つ生薬に黄柏、黄芩(おうごん)、苦参(くじん)などがあります。
黄芩・黄連・黄柏の性質はとてもよく似ています。どれも苦味があって熱を冷まし、余分な湿をとる働きがあります。「黄芩は上焦(じょうしょう)を治し、黄連は中焦(ちゅうしょう)を治し、黄柏は下焦(げしょう)を治す」と言われ、黄連は中焦(みぞおちからへそまで)の清熱に優れた効果を発揮します。清熱作用は全身に作用しますが、特に心や胃の熱によく働き、不眠・動悸・胸のつかえ・下痢・腹痛などに用いられます。
同じ清熱薬である黄芩と一緒に配合されている漢方薬を「瀉心湯類(しゃしんとうるい)」と呼びます。瀉心とは、みぞおちのつかえを取り去るという意味で、このような症状がある方に用いられます。代表的な瀉心湯類として、半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)、黄連解毒湯(おうれんげどくとう)、三黄瀉心湯(さんおうしゃしんとう)などがあります。
湿熱(しつねつ)が原因の下痢には、葛根(かっこん)と一緒に配合された葛根黄連黄芩湯(かっこんおうれんおうごんとう)が用いられます。
陰虚による不眠には阿膠(あきょう)と一緒に配合された黄連阿膠湯(おうれんあきょうとう)が用いられます。
その他熱性の疾患に幅広く用いられていますが、多量に使用すると胃腸を傷つけるので、元々胃腸が冷えている方や弱い方には不向きです。
LINEで完結♪
オーダーメイド漢方治療
LINEで完結♪
オーダーメイド漢方治療
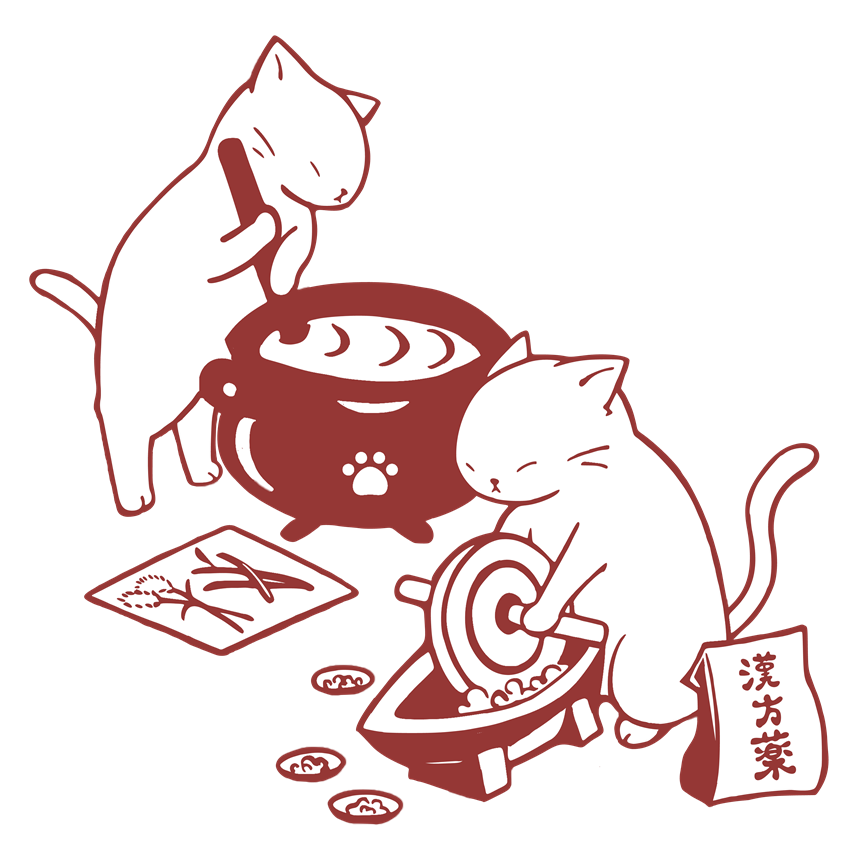
漢方専門の薬剤師があなたに
ぴったりの漢方薬をご提案
まずはLINEより無料の
体質診断をしてみましょう!
― 初回限定 ―
\桃華堂オリジナル缶プレゼント!/
LINE相談について詳しくはこちら ↓

